 |
 |
 |
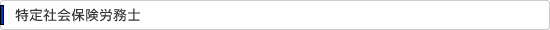 |
 |
| ■特定社会保険労務士制度 |
平成17年6月17日法律第62号により、社会保険労務士法第2条が改正され、特定社会保険労務士制度が平成19年4月1日からスタートすることになりました。
■特定社会保険労務士になるためには試験合格が条件
特定社会保険労務士になるためには、同条で定める紛争解決手続代理業務試験(いわゆる能力担保措置)に合格し、登録事項に付記されることが必要となります。
■特定社会保険労務士の業務は
特定社会保険労務士は(1)地方労働局あっせん調整委員会におけるあっせんの手続きについて紛争の当事者を代理すること。(2)同労働局における男女雇用機会均等法第18条第1項にかかる調停の手続きについて紛争の当事者を代理すること(3)地方労働委員会が行う個別労働関係紛争にかかるあっせんの手続きについて紛争の当事者を代理すること(4)厚生労働大臣が指定する民間紛争解決機関における紛争解決手続きにおいて紛争の当事者を代理すること、の4業務ができます。特定社会保険労務士でないものはあっせん代理業務ができません。
■行政型ADRと民間型ADRではどこが異なるか
行政型ADRとは、上記の(1)〜(3)をいい、民間型ADRとは(4)をいいます。前者は、その紛争の目的にかかる価額に限度がありませんが(つまり、何百万円の紛争でも扱えるということです。)、後者は60万円が限度(超えるときは弁護士と共同受任)とされました。
■当事務所は労働者の立場を考える特定社会保険労務士
ご存知の様に、事業主と労働者の紛争の場合、労働者は比較的に弱い立場となります。当事務所は顧問先を除き、労働者の代理となり、これまで培ってきた経験と知恵を駆使して個別労働紛争代理人として、労働者の要望に適う、権利を守り、労働環境の改善を確保します。 |
| |
| |
| |
|
|

